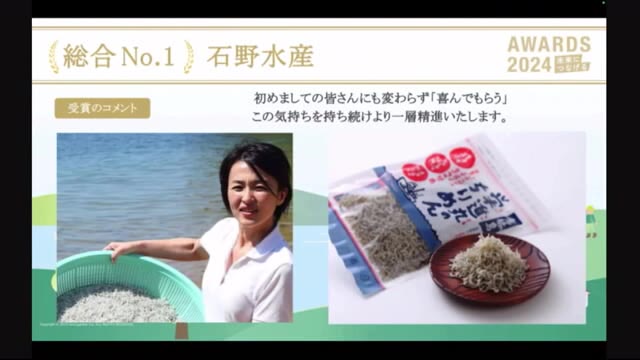当時5歳の小学5年生が地域のハザードマップ作り 西日本豪雨から7年 風化が懸念される記憶をつなぐ
2/4(火) 18:27
西日本豪雨から今年で7年を迎えます。
年々、災害の記憶の風化が懸念される中、自らの力でその課題を解決しようと奮闘する小学生を取材しました。
【住民】
「たぶん災害など起きないと思っていた」
地域住民のリアルな証言に耳を傾ける児童たち…。
【住民】「ああ~木がかかったと思ったら5秒か10秒くらいで一気に溢れて…」
《2018年》
「川の欄干に上流から流れてきた木が詰まったような状況になっています」
2018年、坂町内に甚大な被害を出した西日本豪雨…。
去年10月、復旧・復興が進んだ町内を歩きながら今では想像がつかない当時の状況について一つ一つ学んだでいるのは坂小学校の5年生です。
【児童】「ここもない?」
【住民】「ここもない、流された」
【児童】「ここの道とか削られてた」
【住民】「うん、ここはなかった」
「なんで危ないところに避難路をつくるの?安全なところがないんです西側地区は。全部危険なところ!」
「ということは早く避難しないといけなんです」
国交省の担当者からも砂防ダムの役割や土石流の恐ろしさを学び、当時5歳だった自動は災害から7年目を迎えるいま、ある決意をしています。
【坂小学校5年生】
「橋に岩や木とかがつまって水が流れたというのを一番伝えたいと思った」
【坂小学校5年生】
「いまこうやってきれいになっているから想像がつかなかったところも怖かった。(過去の教訓を)伝えてくれる人もいるけどそれを伝統で伝えていかないと分からないということも伝えて、どんどんいろいろな人に伝えたい」
【向井記者】
「鮮明でなかったあの日の記憶を直接住民から学んだ児童たちは、そのことを自らの言葉で伝えようとオリジナルのハザードマップをつくりました。これから住民たちに発表します」
【児童】
「この紫の丸はバックウォーター現象が起きた場所です。小さい川からの水が大きい川に流れることができずこの場所で水などがあふれた」
3つの地区に分けて作成されたオリジナルのハザードマップは、これまでに作られたハザードマップに児童たちが歩いて気づいた情報などを追加することにこだわったといいます。
【児童】
「黄色いところは前回の災害で水没したところ。赤い線は氾濫する恐れがあるので危険。特に緑の線を使う地域の人は早めに避難する必要があります」
発表を聞いた地域住民たちは…。
【地域住民】
「(年月が経ち)忘れかけているところを思い出させてくれてありがとうございました」
「今度自主防災の訓練が地区であるが、ぜひ借りて使わせてもらう」
【発表を聞いた4年生?】
「いままで安全だと思っていた地域も災害の被害にあっていてびっくりした。
(学んだことを)これから災害があったときに生かしたい」
”自分たちは当時のことをあまり知らない”でも”坂町みんなの命を守りたい”。
将来を担う若い世代の行動がまた一つ、地域の防災意識を強くしました。
年々、災害の記憶の風化が懸念される中、自らの力でその課題を解決しようと奮闘する小学生を取材しました。
【住民】
「たぶん災害など起きないと思っていた」
地域住民のリアルな証言に耳を傾ける児童たち…。
【住民】「ああ~木がかかったと思ったら5秒か10秒くらいで一気に溢れて…」
《2018年》
「川の欄干に上流から流れてきた木が詰まったような状況になっています」
2018年、坂町内に甚大な被害を出した西日本豪雨…。
去年10月、復旧・復興が進んだ町内を歩きながら今では想像がつかない当時の状況について一つ一つ学んだでいるのは坂小学校の5年生です。
【児童】「ここもない?」
【住民】「ここもない、流された」
【児童】「ここの道とか削られてた」
【住民】「うん、ここはなかった」
「なんで危ないところに避難路をつくるの?安全なところがないんです西側地区は。全部危険なところ!」
「ということは早く避難しないといけなんです」
国交省の担当者からも砂防ダムの役割や土石流の恐ろしさを学び、当時5歳だった自動は災害から7年目を迎えるいま、ある決意をしています。
【坂小学校5年生】
「橋に岩や木とかがつまって水が流れたというのを一番伝えたいと思った」
【坂小学校5年生】
「いまこうやってきれいになっているから想像がつかなかったところも怖かった。(過去の教訓を)伝えてくれる人もいるけどそれを伝統で伝えていかないと分からないということも伝えて、どんどんいろいろな人に伝えたい」
【向井記者】
「鮮明でなかったあの日の記憶を直接住民から学んだ児童たちは、そのことを自らの言葉で伝えようとオリジナルのハザードマップをつくりました。これから住民たちに発表します」
【児童】
「この紫の丸はバックウォーター現象が起きた場所です。小さい川からの水が大きい川に流れることができずこの場所で水などがあふれた」
3つの地区に分けて作成されたオリジナルのハザードマップは、これまでに作られたハザードマップに児童たちが歩いて気づいた情報などを追加することにこだわったといいます。
【児童】
「黄色いところは前回の災害で水没したところ。赤い線は氾濫する恐れがあるので危険。特に緑の線を使う地域の人は早めに避難する必要があります」
発表を聞いた地域住民たちは…。
【地域住民】
「(年月が経ち)忘れかけているところを思い出させてくれてありがとうございました」
「今度自主防災の訓練が地区であるが、ぜひ借りて使わせてもらう」
【発表を聞いた4年生?】
「いままで安全だと思っていた地域も災害の被害にあっていてびっくりした。
(学んだことを)これから災害があったときに生かしたい」
”自分たちは当時のことをあまり知らない”でも”坂町みんなの命を守りたい”。
将来を担う若い世代の行動がまた一つ、地域の防災意識を強くしました。