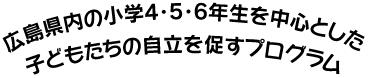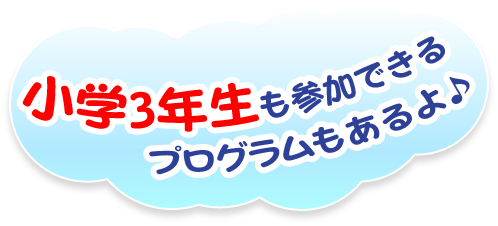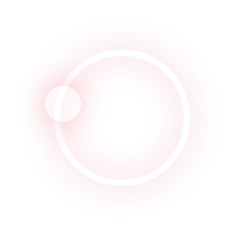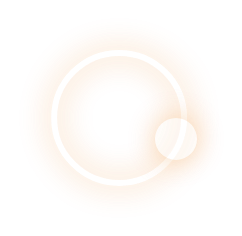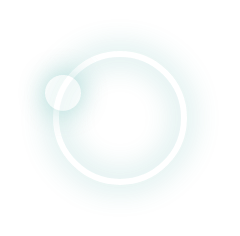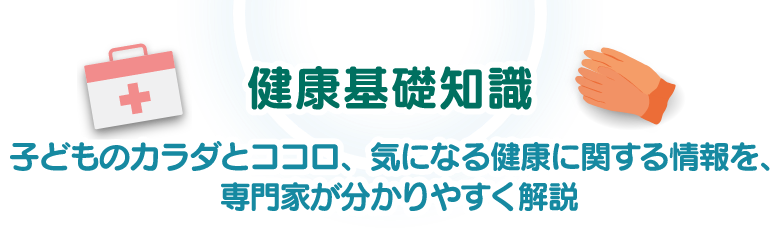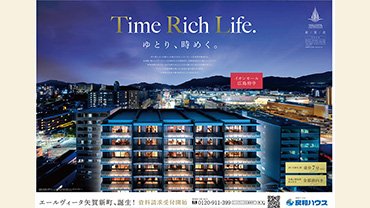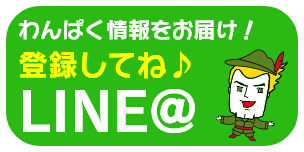2025年4月16日(水)
【素朴な疑問シリーズ】長引く咳に注意!百日咳の基礎知識といま大切なこと

近年、百日咳の患者数が再び増加傾向にあります。特に10代後半から大人にかけての感染が目立ち、軽症で見逃されやすいため、知らぬ間に小さな子どもや乳児へうつしてしまうケースも少なくありません。乳児にとっては命に関わることもあるこの病気。かつてはワクチンの普及で激減した百日咳が、なぜまた増えているのでしょうか?今回は、百日咳の症状、原因、予防法についてお伝えしていきます。

世界と日本、百日咳は今も深刻

世界では毎年約1,600万人が百日咳に感染しており、その大半が発展途上国の小児です。年間約19.5万人が命を落としているという報告もあり、いまだに予防接種が十分に行き渡っていない地域では深刻な問題となっています。
日本でも、1950年にワクチンが導入されるまでは、年間10万人以上の患者が発生し、その約10%が死亡していました。しかし、DPT(ジフテリア・百日咳・破傷風)三種混合ワクチンの普及により、1970年代には日本の百日咳罹患率は世界で最も低い水準にまで下がりました。
ところが近年、再び患者数が増加傾向にあります。2000年代後半から徐々に増え始め、2016年には15歳以上の患者が全体の4分の1を占めるまでに。また、コロナ禍以降の2024年中ごろから再び増加に転じています。その要因は、特にワクチン接種から年数が経った中高生や大人の感染と考えられています。大人は軽症のことが多いため、知らずに赤ちゃんや子どもへうつしてしまう構図が近年の流行の一因といえるのです。

3つのステージで進行する症状

百日咳の症状は段階を追って変化していきます。それぞれの時期に特徴があるため、見極めが大切です。
● ステージ1:風邪と見分けがつかない「カタル期」
最初は鼻水や咳といった軽い風邪のような症状から始まります。この時期は症状が目立たないものの、最も感染力が高いため注意が必要です。
● ステージ2:特徴的な咳が出る「痙咳(けいがい)期」
しばらくすると、連続した咳のあとに「ヒューッ」と息を吸い込む笛のような音が特徴的に現れます。夜間に多く、吐き気や顔の内出血などを伴うこともあります。乳児では無呼吸やけいれん、重症化リスクが非常に高いため、特に注意が必要です。
● ステージ3:長い戦いの「回復期」
咳は少しずつ減っていきますが、完全に落ち着くまでには2~3カ月かかることも。大人の場合は軽症で、長引く咳だけで終わることが多いため、見逃されやすいです。

どうやって診断?どうやって治す?

診断は、症状の経過や血液検査などで行います。白血球、特にリンパ球が異常に増えることがあり、医師が百日咳を疑う材料になります。
治療には、マクロライド系抗生物質(エリスロマイシン、クラリスロマイシンなど)が使われます。早期であればあるほど効果的で、治療から約5日で菌の排出も止まるとされています。赤ちゃんには、作用時間が非常に長い抗生物質アジスロマイシンが推奨されるケースもあります。

ワクチンこそ最大の防御

百日咳の予防には、ワクチン接種が最も有効です。日本では現在、DPT-IPV(百日咳・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ)の四種混合ワクチンが定期接種として導入されており、生後3カ月以降に計4回接種するスケジュールが組まれています。ただし、ワクチンによる免疫は時間とともに弱まり、接種後4~12年で免疫効果が低下するとされています。
そのため、赤ちゃんだけでなく、大人も含めたブースター接種も視野にいれることが必要です。12歳以上の追加ワクチン接種も推奨されています。

長引く咳はサインかも?学校での対応は?

百日咳は、学校保健安全法上「第2種感染症」に指定されており、特有の咳がなくなるか、5日間の適切な抗菌薬治療が完了するまで出席停止となります。感染防止のためにも、早期の受診と治療が大切です。
かつては「昔の病気」と思われていた百日咳ですが、今また身近な感染症として注目されています。特に症状が軽く見過ごされがちな大人が、ワクチン未接種の乳児へ感染させてしまうリスクは見逃せません。長引く咳は、百日咳のサインかもしれません。自身の健康を守るだけでなく、まわりの大切な人を守るためにも、ワクチンの接種や早期受診を心がけましょう。

出展
国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト
https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ha/pertussis/010/pertussis.html?utm_source=chatgpt.com